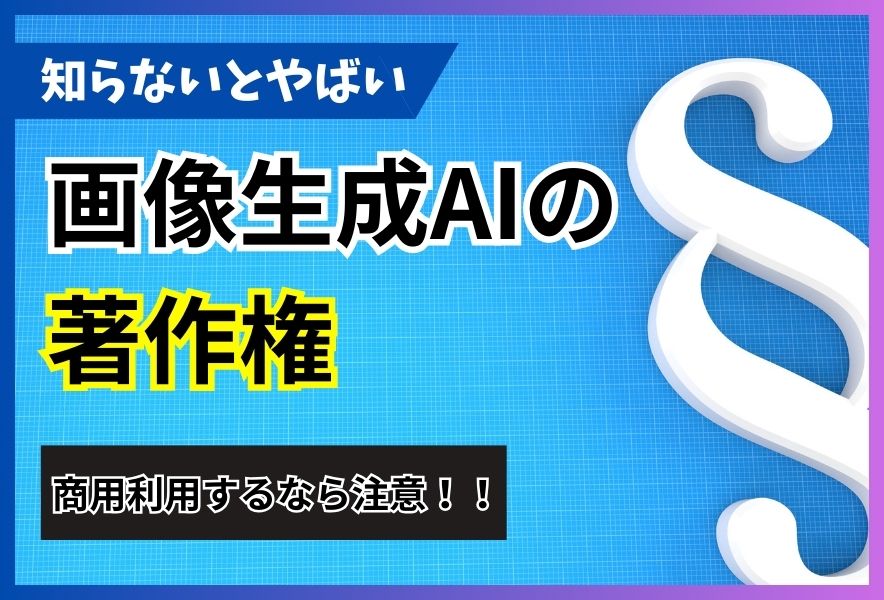近年、画像生成AI技術が急速に進化し、さまざまな領域で活用されはじめています。
そんな中、Appleの最新AI技術を活用した画像生成ツール「Image Wand / Image Playground」 が注目を集めています。
本記事では、画像生成AIツールの概要や著作権問題、商用利用の可否、さらに使用上の注意点について分かりやすく解説します。
ぜひ、最後までご覧ください。
Image Wand / Image Playgroundとは?
「Image Wand / Image Playground」は、Appleが開発している最先端のAI技術を用いた画像生成AIツールです。テキストや写真を参照に、AIがそれに対応した画像を自動生成してくれます。写真風のリアルなものからイラスト風のものまで、さまざまなスタイルのビジュアルを作り出せる点が大きな魅力です。
このような画像生成AIは、クリエイターやマーケターなど、ビジュアルを扱う多くの人にとって有用なツールになり得ます。しかし、その一方で「著作権侵害は起きないのか?」「商用利用して大丈夫なのか?」といった不安の声が上がるのも事実です。
著作権問題と商用利用は大丈夫?
Image Wand / Image Playgroundなどの画像生成AIツールに関して、よくある疑問を整理してみましょう。
著作権問題は大丈夫か?
日本の著作権法においては、著作権侵害が成立するためには「類似性」と「依拠性」という2つの要件を満たす必要があります。
類似性とは、生成された画像が既存の著作物とどれだけ似ているかを指します。著作権法において、類似性が認められると、著作権侵害の可能性が高まります。
具体的には、以下の点が考慮されます。
・表現上の特徴:生成された画像が、既存の作品の「表現上の本質的な特徴」をどれだけ直接的に感得できるかが重要です。単なるアイデアやテーマの類似ではなく、具体的な表現方法が問題となります。
・判例の影響:過去の裁判例では、著作権侵害が成立するためには、生成物が既存の著作物と「同一または著しく類似」している必要があります。このため、生成された画像がどの程度既存の作品に似ているかが、法的判断の基準となります。
依拠性は、生成された画像が既存の著作物を参照しているかどうかを示します。依拠性が認められると、著作権侵害のリスクが高まります。
以下の要素が重要です。
・既存著作物の利用:画像生成AIは、大量の画像データを学習することで新たな画像を生成します。この際、既存の著作物を認識し、それを基に新しい画像を作成するため、依拠性が認められる場合があります。また、既存著作物の名前をプロンプトに入れたり、画像を参照にすると、依拠性が認められるリスクが高まります。
・無断使用のリスク:学習データセットの詳細が公開されていない場合、生成された画像が著作権で保護された作品を無断で使用している可能性があります。この場合、依拠性が認められ、著作権侵害とされるリスクがあります。
商用利用はできるのか?
画像生成AIツールの商用利用に関するポリシーは、ツールによって大きく異なります。基本的には、それぞれ独自の利用規約を設けているので、しっかり確認をしてから使用するのが重要です。
Appleが提供するImage Wand / Image Playgroundについては、現時点で商用利用が可能かどうかの明確な記載がありません。Apple製品の一般的な利用規約を参考にすると、個人利用の範囲を超えた商用利用については制限がある可能性も考えられます。
商用利用を検討している場合は、必ず最新の規約を確認する、またはAppleに問い合わせすることをおすすめします。
著作権侵害を避けるための注意点
画像生成AIを利用する際に著作権侵害のリスクを最小限に抑えるためのポイントをいくつか紹介します。
- プロンプトの工夫:特定の作家名やキャラクター名を直接指定するプロンプトは避け、スタイルや雰囲気を言葉で表現するようにしましょう。
- 生成結果の確認:生成された画像が既存の著作物に酷似していないか注意深く確認しましょう。具体的にはgoogleなどで画像検索をかけ、類似のものがないか確認するのがおすすめです。
- 利用規約の確認:AIツールの利用規約はツールごとに異なります。初めて使用するツールは利用規約を確認する習慣をつけましょう。
- 商用利用の明示:商用目的で使用する場合は、そのAIツールが商用利用を許可しているかを事前に確認してください。一般的には、利用規約やプラン比較ページに記載してあります。
画像生成AIの法的枠組みはまだ発展途上であり、今後も変化していく可能性が高いです。最新の情報を常にチェックし、安全に活用することが重要です。
炎上リスクなど、画像生成AIを使用する上での注意点
たとえ著作権的に問題がなく、商用利用が可能だとしても、社会的な反応や炎上リスクに注意を払う必要があります。
最近では「AIが生み出した作品」に対して否定的な感情を持つ人や、「既存のアーティストの仕事を奪う」といった議論が起こるケースも見受けられます。次の点に留意しましょう。
AI作品であることを明示するかどうかの検討
AIが生成した作品であることを公表するか否かは、炎上を回避するうえで大きなポイントになります。オリジナルの手描きや撮影と混同されることへの抵抗感を持つユーザーもいるため、生成過程を開示することで透明性を高めるのも一つの方法です。ただし、プロジェクトの性質やクライアントの意向によっては、「AI活用」を全面的に押し出さない方が良い場合もあるため、公開方針を慎重に決めましょう。
AI生成物の編集・加工
AIによって生成された画像をそのまま使用するのではなく、イラストレーターやデザイナーが手直しを加えることで、品質を高めるだけでなく、AI特有の違和感を解消し、倫理的な問題や権利侵害のリスクを低減できます。
アーティストやクリエイターコミュニティへの配慮
画像生成AIの登場によって、従来のアーティストやデザイナーの仕事が奪われるのではないか、という懸念は根強く存在します。実際にAIの台頭が一部のイラストレーターや写真家にとって脅威となる側面があるのも事実です。
「仕事を奪う」ツールではなく、クリエイターの作業を補助したり、アイデアの幅を広げる手段であることを周囲に理解してもらえるよう、情報を発信しながらコミュニケーションを取ることが大切です。
まとめ
- Image Wand / Image Playground は、商用利用の可否についての詳しい明記がない。(執筆時点:25/02/27)
- 一般的な画像生成AI同様に、著作権問題は、生成した作品の「類似性」と「依拠性」が焦点になります。
- 著作権上問題がなくとも、炎上リスクや社会的な反発がある可能性を踏まえ、コミュニケーションや透明性に気を配ることが重要です。
画像生成AIは多くの場面で役立つ便利なツールですが、正しいルールを守らなければ、著作権問題や炎上など取り返しのつかない事態を招きかねません。最新情報を確認しながら、安全かつ有益に活用していきましょう。